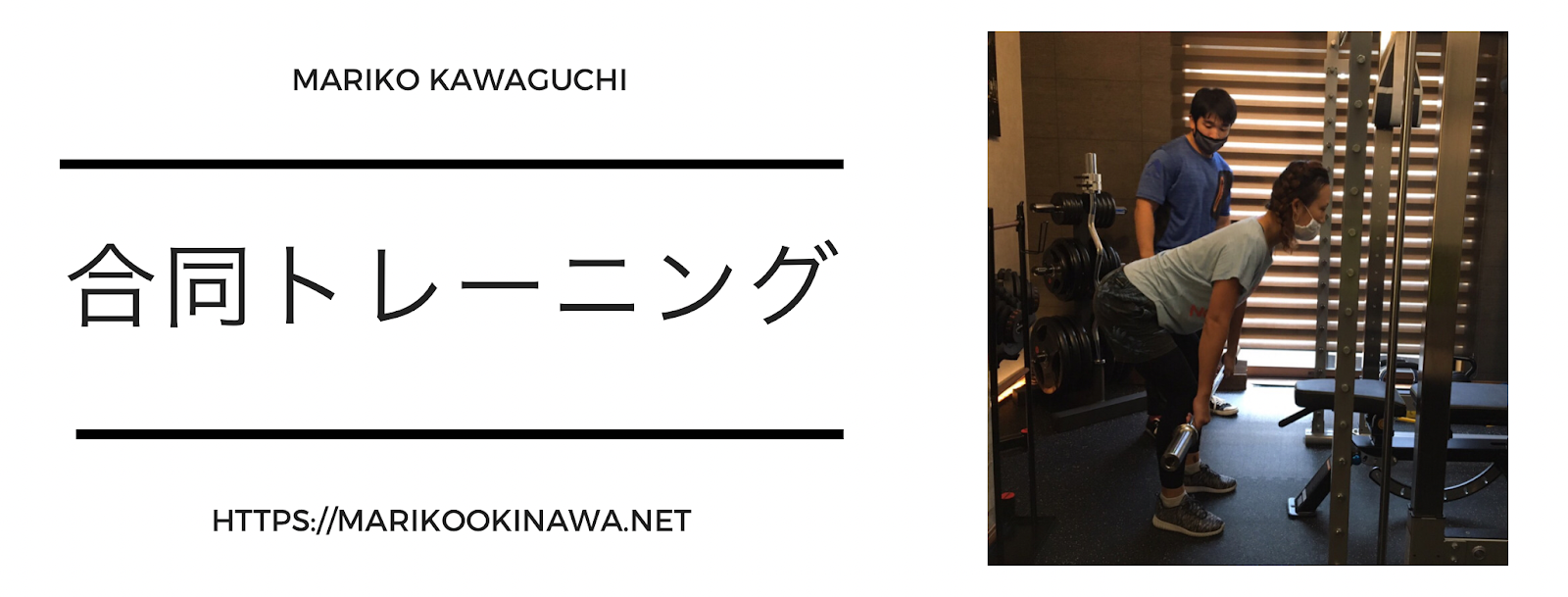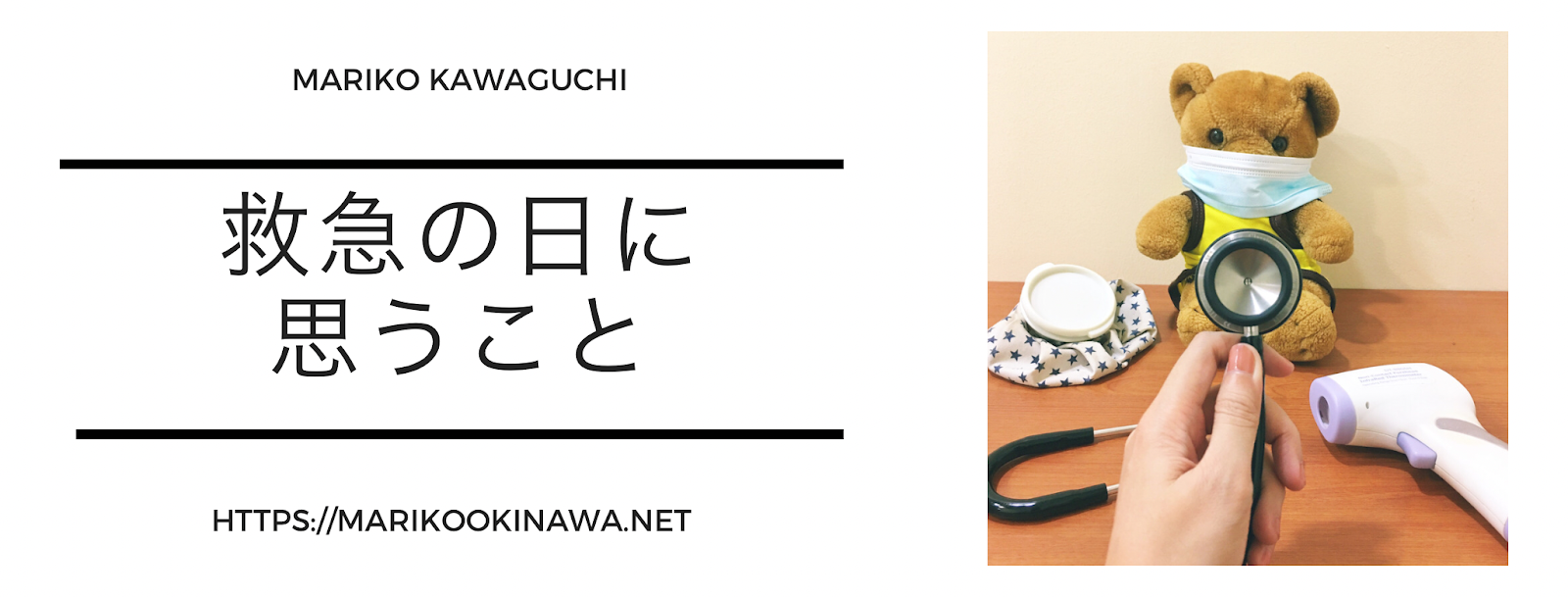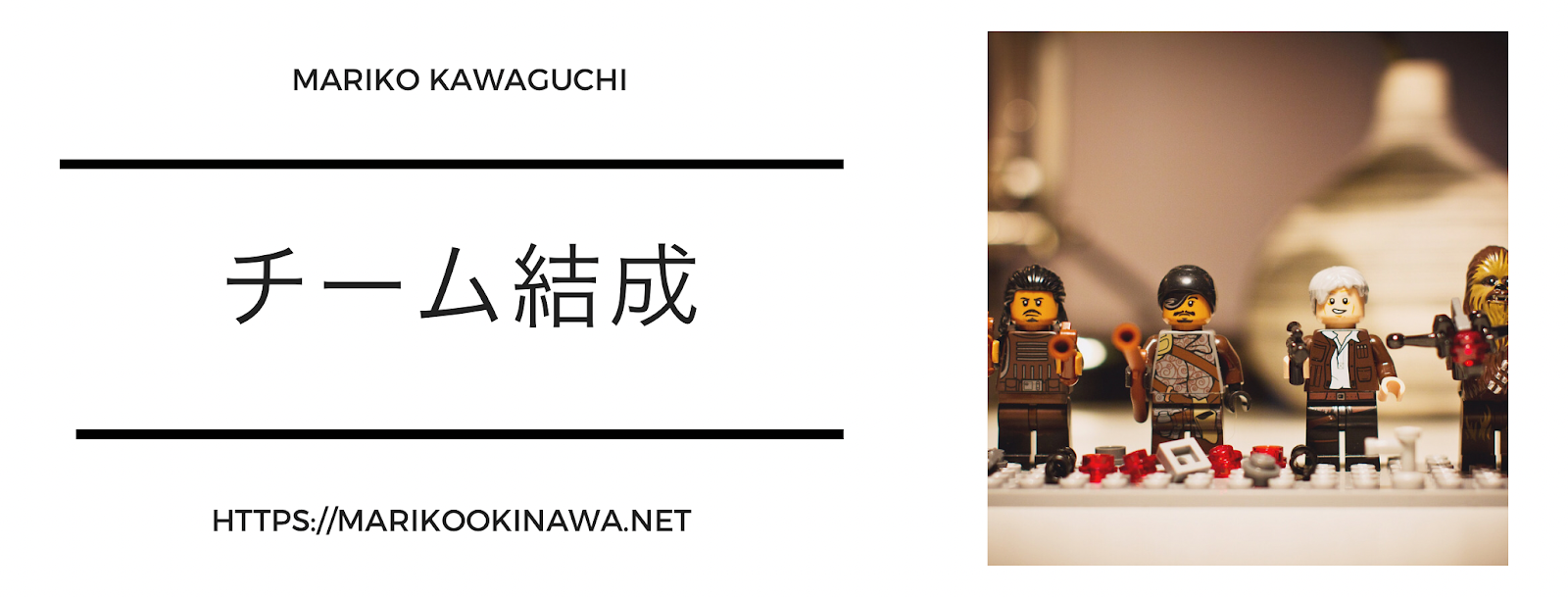9月9日は『救急の日』ですね。
元気に何もなく毎日を過ごしている人にはあまり馴染みがないかもしれないけど…
運動指導の仕事をしていると、過度な運動で体調が悪くなったり激しいレッスンで怪我をする人がいたり、高齢者も多く持病を持つ人もおられるので、119番通報や救急車、AEDや心肺蘇生などは私にとっては比較的身近なことです。
現在7歳の長男が2歳の頃にスキー場で初めて熱性けいれんを起こし、119番通報したけど山奥すぎて救急車がすぐに来れずドクターヘリで搬送されたことがあります。

その後も頻繁に無熱性けいれんを起こすようになり、検査の結果小児てんかんと診断されました。
月に何度も発作(けいれん)が起きるので、その度に救急車を呼び、1週間に2回ぐらいのペースで救急搬送という時期が2カ月ほど続きました。
車を運転中に救急車が来ると当たりのように道を譲るけど、実際に救急車に乗ってる患者側として救急車の中からその景色を見ていると、
「どの車も自分たちのために道を譲ってくれている」
「早く病院に着いて1秒でも早く手当てを受けられるようにみんなが協力してくれている」
と感じて、感謝しかない気持ちになります。
道を譲ってくれてた車には、自分たちも急いでどこかに向かっている人もいたかもしれません。
それでもサイレンが聞こえたら優先して道を譲るという、みんなが当たり前にしている行動がどれだけありがたかったか、忘れることはありません。
だからこそ

こういったことは本当にやめてもらいたいと思います。
私の住んでいる大阪府は、人口あたりの救急出場件数が全国でもトップクラスとのこと。
そして搬送人員のほぼ半数は65歳以上の高齢者だそうです。
上記の画像や、画像をクリックして見られる記事のような利用例はほんの一部かもしれませんが、本当に救急車が必要な人のために、ひとりひとりがきちんと考えて行動してほしいです。
息子がけいれん発作を起こす度に救急車を呼び、搬送先で検査を受けたら異常なしで帰宅するということの繰り返しだったので、
「主治医からは、発作が起きたら救急車!と言われてるので毎回呼んでますが、結局いつも異常なしで帰ってくるので、今後も本当に救急車要請していいのか…」
と救急隊員に尋ねたことがあります。
救急車の間違った使い方のせいで、本当に救急救命が必要な人の元に救急車が行けないと聞いたこともあったので。
その時に救急隊員は、
小さなお子さんがけいれん発作を起こしたらとても心配だから、この先も同じようなことが起きたらすぐに救急車を呼んでください
救急車が到着して少しでもお子さんとお母さんが安心してくれれば良いです
発作が起きたら救急車!で、いいし、搬送先から毎回異常なしで帰って来られて良かったです
と言ってくれました。
そんな気持ちで救急救命に尽力されている人の気持ちがあると知って、一層「救急車は正しく使わなければならない」と思うようになりました。

↑
総務省消防庁に【救急車利用マニュアル】というものがあります。
救急車のイラストをクリックして、一度見てみてほしいです。

↑
今日の読売新聞朝刊より。
コロナ渦での救急医療について載っていました。
てんかんと診断された息子ですが…
服薬治療を終え、幸いにも約5年間発作が起きることなく毎日元気に過ごしています。
余談ですが、
救急車が来れないほどの山中でドクターヘリ搬送していただきましたが、最寄りの救急病院まで車で2時間半だと言われたところを、ヘリなら7分で到着しました。
ドクターヘリすごいです。